児童思春期とは
 当院の児童思春期外来では、6~15歳の小学生・中学生のお子様を診療します。
当院の児童思春期外来では、6~15歳の小学生・中学生のお子様を診療します。
子どもに見られるさまざまな問題行動、精神・身体症状をもとに、主に発達的な観点から診断・治療を行います。
また、この年代の子どもは、高校生や大学生・大人と比べて小さな社会の中で生きています。核家族化、一人っ子の増加、ご近所付き合いの減少といった家族・社会の在り方の変化も重なり、あるコミュニティで適応できない場合に「逃げ場がない」「相談できる人がいない」「大きなストレスを感じてしまう」ということが少なくありません。
発達障害、適応障害、うつ病などをはじめとするさまざまな疾患に対応しておりますので、どうぞ安心してご相談ください。
受診対象
児童思春期外来の対象となるのは、6~15歳の中学生までのお子様を対象させて頂いております。
次にご紹介する症状・お悩みがございましたら、お気軽にご相談ください。
対象となる主な症状・
悩み・疾患
主な症状・悩み
- 授業、自宅学習に集中できない
- 忘れ物が多い
- 強いこだわりがある、融通がきかない
- じっとしていられない
- なかなか友達ができない
- いつも一人遊びをしている
- 集団行動が苦手
- 思ったことを考えずに実行してしまう
- 人を傷つけることを言ってしまう
- 読み、書き、算数などが極端に苦手
- 朝起きられない
- 寝つきが悪い、夜中に目が覚める
- ゲームがやめられない
- 不安や緊張で動悸・息苦しさを感じる
- すぐに嘘をついてしまう
- 気分の落ち込みが続いている
- 好きな食べ物、趣味などへの関心の低下
- 情緒不安定、すぐにカッとなる
- 学校に行けない、教室に入れない
- 引きこもり
- 家庭内暴力
- リストカットなどの自傷行為
- 髪の毛を抜く
- 家庭では話せるのに、学校では話せない
考えられる疾患
自閉症スペクトラム症
先天的な脳機能障害を原因とする発達障害の1つです。対人関係、コミュニケーションなどに困難を伴います。相手の意向を汲み取れない、言葉・言語の遅れ、こだわりの強さ、癇癪・自傷行為などが見られます。
注意欠陥多動性障害
発達障害の1つです。授業中にじっと座っていることができない、忘れ物・不注意が多い、お喋りを注意されてもやめられない、興味のないことに集中できないといった特徴が見られます。
学習障害
発達障害の1つです。読み・書き・算数などにおいて困難が見られます。特定の分野において大きな遅れが見られる場合には、ご相談ください。適切な支援が受けられないと、お子様の自信喪失にもつながります。
適応障害
ストレスを主な原因とします。不安や憂うつ、イライラ、思考力・集中力の低下、不眠、食欲不振などの症状が見られます。「子どももストレスを抱えている」ことを、私たち大人は十分に理解することが大切です。
うつ病
学校・家庭の人間関係などによるストレスを主な原因として発症します。ひどく気分が落ち込んだ状態が数週間以上続きます。好きだったものに興味・関心がなくなる、不眠/過眠などの症状も見られます。
統合失調症
まわりには聞こえない声が自分だけ聞こえる「幻聴」、誰かに見張られている等の「妄想」などにより、頭の中がいっぱいになる病気です。進行すると、思考力の低下、独り言の増加、人との関わりの回避なども見られます。
自律神経失調症
自律神経のバランスの乱れによって、疲労感・倦怠感・めまい・耳鳴り・吐き気・下痢・便秘などの身体症状、イライラ・焦り・不安・孤独感などの精神症状が現れます。
摂食障害
なんらかの原因によって、通常の食事ができなくなる病気です。よく知られるのが「痩せたい」という強い想いや認知の歪みから起こる拒食ですが、意図的に吐く行為に至ったり、反動で過食・一気食いが生じることもあります。
分離不安障害
親などの愛着のある人(あるいは場所)から離れることに強い不安を覚えます。不登校、引きこもりの原因になることが少なくありません。「甘えだ」「親離れできていない」と決めつけず、一度ご相談ください。
チック症
意図せず突然、癖のように出てしまう言葉や動きがある状態です。「アッ」等の意味のない声が出る・卑猥な言葉を言ってしまう音声チック、白目をむく・鼻を動かす・首をすくめるなどの運動チックがあります。
トゥレット症候群
1つ以上の音声チック、複数の運動チックが1年以上続いている状態です。遺伝的要因が関与していると考えられています。一方、性格・しつけなどが発症に影響することはありません。
緘黙症
家庭以外の場所で、言葉を話せない状態です。多くの場合、家庭では何の問題もなく話せます。本人は学校などでも話したいと思っていることが多く、そのことがストレスとなり、うつ病を引き起こすこともあります。
特に当院で相談の多い症状
対人関係・コミュニケーションの困難
 自閉症スペクトラム症などで見られるのが、対人関係・コミュニケーションの困難です。
自閉症スペクトラム症などで見られるのが、対人関係・コミュニケーションの困難です。
お子様の場合、主に以下のような傾向が見られます。
- 視線が合わない
- 呼んでも振り向かない
- 集団行動が苦手
- 一人遊びが多い
- 言葉の発達の遅れ
- 言葉のキャッチボールが苦手
- 相手の意図を汲み取れない、イライラさせてしまう
- 特定のもの・手順・場所などに強くこだわる
- 特定の音、光などに過度に反応する
- 癇癪、自傷行為
不注意・多動性・衝動性
 注意欠陥多動性障害では、不注意・多動性・衝動性といった特徴が認められます。
注意欠陥多動性障害では、不注意・多動性・衝動性といった特徴が認められます。
お子様の場合、主に以下のような傾向が見られます。
- 授業中などにじっとしていられない
- 忘れ物、不注意が多い
- よくものを失くす
- 課題などを計画的に行うことが難しい
- お喋りを注意されてもやめられない
- 机、ランドセルの中、部屋などの整理整頓が苦手
- 順番を待てない
- 考える前に行動に移してしまう
- 友達を傷つけることを言ってしまう
- 興味のないことに集中できない
読み・書き・算数などの
困難・遅れ
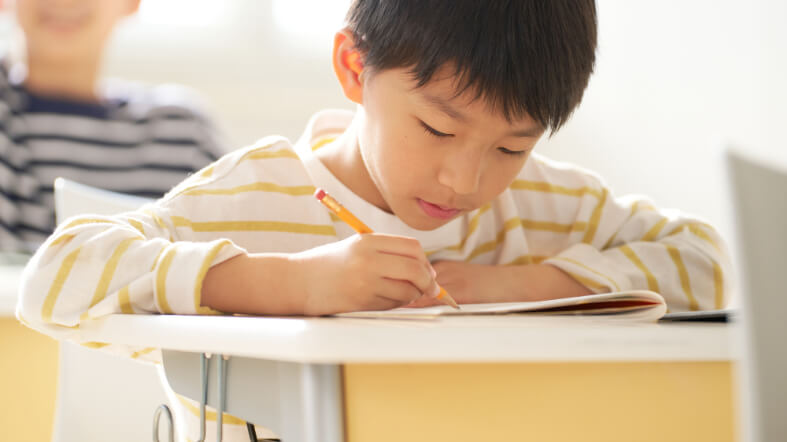 学習障害では、読み・書き・算数などにおける困難、まわりの子どもからの遅れが認められます。
学習障害では、読み・書き・算数などにおける困難、まわりの子どもからの遅れが認められます。
お子様の場合、主に以下のような特徴・困難が見られます。
- 話し始めるのが遅い
- 言葉の理解の遅れ
- 文字を書く、読むのが苦手
- 音読がたどたどしい、読み間違える
- バランスよく字を書くことが難しい
- 黒板の内容を授業中に書き写し切れない
- 計算、文章問題が苦手
- 数、数字の概念を理解できていない
- 九九が覚えられない
- 時計が読めない
- 特定の分野のみ、大きな遅れが見られる
主な検査について
 症状、お悩み、生活状況などをお伺いした上で、以下のような検査を行い、診断します。
症状、お悩み、生活状況などをお伺いした上で、以下のような検査を行い、診断します。
人格検査
現在のこころの状態を客観的に評価する検査です。
バウムテスト、ロールシャッハテストなどがあります。
知能検査
知的能力を調べる検査で、IQを把握します。
特徴を整理したり、必要となる支援を判断するのに役立ちます。
発達検査
発達の特性の有無・程度などを客観的に調べる検査です。
お子様ご本人だけでなく、保護者様・学校の先生にもご回答いただくことがあります。
よくある質問
発達障害とは、どのような障害ですか?
生まれつきの脳の機能障害によって現れる精神障害の総称です。自閉症スペクトラム症、注意欠陥多動性障害、学習障害などに分類されます。原因はあくまで脳にあり、性格や育て方などは発症に影響しません。
発達障害は、治るものなのでしょうか?
脳の機能障害が原因であるため、根本的な治療法はありません。しかし、お子様の得意・不得意を含めた特徴を把握し、適切な環境調整・サポートを行うことで、発達障害に伴う困難・生きづらさなどを軽減することは可能です。当院で行う治療も、その環境調整やサポートが中心となります。
子どもに発達障害の傾向が見られますが、診断名がつくのがこわいような気もします。
お気持ちはよく分かりますが、辛い想いをしているお子様に適切な支援をし、困難・生きづらさを和らげるためにも、一度ご相談ください。また、発達障害はすぐに診断名がつくわけではありません。経過を見ながら、継続的にお子様をサポートしていきます。
子どもに薬を使うのには抵抗があります…。
基本的に、初診でお子様にお薬を処方するということはありません。またお子様・保護者様のご希望を尊重した治療を行って参りますので、ご遠慮なく医師にお伝えください。ただ、うつ病などの治療において薬物療法の必要性が生じることもあり、その場合はおすすめさせていただくこともあります。
子どもが受診に抵抗があるようです。どうすればいいでしょうか?
親子でご来院いただくことが理想ではありますが、難しい場合には、まず保護者様だけ、ご相談にいらしてくださっても構いません。
不登校や引きこもりでも、相談できますか?
はい、もちろんです。不登校や引きこもりの背景にある心理状態やお悩み、あるいは病気・障害の有無などを調べ、適切な治療や支援を行って参ります。







